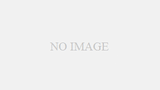2年前に襲名。第13代目市川團十郎 白猿。
市川團十郎家は江戸歌舞伎の創始者であり、最も権威がある家柄の一つ。
林修
「市川團十郎さんの家系図をまず…。すごい家系図ですよね。
改めてご自身の家系図ご覧になって?」
市川團十郎
「まあ親戚しかいないんで、何とも思わないんですけれども。(笑)
(松)たか子ちゃんだって若い時から知ってますし。
(松本)幸四郎さんだって、この前まで仲良く喋ってましたし。一緒に舞台出てましたしね。
で、(松本)白鵬のおじさんは、一緒にこの間まで出てくださって」
林修「もう我々から見ると雲の上の方々がみんな親戚って感じなんですね?」
市川團十郎「歌舞伎界全員親戚です」
普段の日常生活
ブログの更新は1日20回以上
そんな歌舞伎の最高峰市川團十郎の意外なライフワークが…
林修「あの、非常に熱心にブログを更新されるなぁと」
市川團十郎「ああ、そうですか」
市川團十郎の日常をアップするブログ。とにかく投稿数が多いと話題で、1日20回以上は当たり前。
これまで11年間に投稿した回数は、なんと9万9000回以上。
林修「今日もスタッフが調べたところによると、すでにもう14回更新されてると(15時時点)」
長女は俳優としても活躍…役作りのため毎日アップルパイを焼く
林修「お嬢さんと寝られるんですね?」
市川團十郎「昨日は一緒に寝ていい?って言われたんで。いいよつって。はい。一緒に寝て」
林修「え、お嬢様、中学生?」
市川團十郎「なりましたね、中学に」
林修「あ、でも中学生のお嬢さんと父親が一緒に寝るって、世間的にはレアなケースですね」
市川團十郎「あ、もう全然世間を見てないですから、分からないです」
團十郎の長女市川ぼたん(13歳)。
現在は俳優としても活躍しており、日曜劇場ブラックペアンシーズン2にも出演した。
演じたのは洋菓子店の孫娘。アップルパイを祖父の代わりに作る役柄。
役作りのため撮影の2か月前から市川ぼたんは家であることをしていたという…
市川團十郎
「もう、全く知らなかった。ブラックペアンに出ることは知ってたんですけど。
撮影する2か月くらい前から、なぜか娘がアップルパイをずっと毎日焼く。
それでなぜか「パパ食べて」と。
毎日なぜかアップルパイ。
どうしてこんなに好きなんだろう?と思って。結局、深くは聞かなかったんですよ。
「美味しいね」とか「今日は甘いね」とか。まあ、そんな話はさせてもらったんですけど。
まさかそれでブラックペアンが放送されてる時に、放送を生で見てた時に、娘がアップルパイ焼いてるから、「マジか?このことか」と思ってツイッターでやったらば、二宮君もそれを見てて。
それで、「そんな前からアップルパイ作ってくれてありがとうございました」っていうのをなんかリプライしてくれて」
子どもたちから見たパパ…迫力ない、かわいい、そんなに怒らない
そんな團十郎パパのことをどう思っているのか?
長女・市川ぼたん13歳と長男・市川新之助11歳にインタビュー。
自宅での團十郎パパは…
新之助くん
「舞台を観ている方々は父の迫力がすごいなとか思うと思うんですけど。
(家では)迫力はないですね(笑)。
迫力というか、やっぱ包み込んでくれる感じ?が強いですね」
市川ぼたん
「3人でゲームとかをしていると、一番悔しがっていたりとか。
なんか感情を一番表に出すのは父なんじゃないかなと思って。
なんかちょっと、かわいい。
なんか、パパ=かわいいっていう印象が自分の中ですごいなんか強いんですよ」
市川新之助
「あ、怒られたりすることはたまにありますけど。そんなないですね。
3週間に1回か、2週間に1回位です」
スタッフ「新之助さんの反抗期は?」
市川新之助
「たぶん、ないですね。パパって筋肉ムキムキなんですよ。
反抗したら、もうボコボコにされそうなんで」
子どもたちとはよく喋る…世の中のこと全て(芝居、投資、選挙、海外の話など)
林修「いやでも本当にお2人はお父さんのことが大好きで、尊敬しているってことがしっかり伝わってきて…」
市川團十郎「だから一緒に寝れるんです」
林修「あと言語化する能力がとっても豊かで。やっぱり家族でよくお話をなさるんですか?」
市川團十郎
「ああ、よく喋りますね。もうだから、芝居の話。稽古の話。日本の話。海外の話。投資の話。会社の話。もう全部話します。全部話します。
選挙の話。日本の選挙。自民とね…の話。
海外のトランプと…この間の民主党と共和党の話とか。もう全部話します」
林修「もう大人として扱って?」
市川團十郎「大人ですもん、2人は」
林修「まあ、今の話聞いてるとそうですね」
市川團十郎
「はい。もうちゃんとしてるんで。これはもうホント(妻・小林)麻央のDNAかな?と。
僕はもうこのぐらいの時もうチャランポランでしたからね」
林修「まあそれは、僕がもうどうこういう話じゃないんですけど」(笑)
豪快エピソード…全く知らない一般家庭にピンポン!
そう。市川團十郎といえば、若き日の海老蔵時代から伝説的なエピソードが多く残る人。
例えば…
全く知らない一般家庭にピンポンを押して突撃!
市川團十郎
「例えばですと、(妻・小林)麻央とね。あのー昔自転車よく乗ってたんです。
老後はこんなとこで住みたいねと思って話してたところがあって。
そこが1人で麻央が帰った後に、1人で通ったらば空き地があったんですよ。
どうなんだろ?売ってんのかな?買えんのかな?と思って、隣の家にピンポーンつって。
「いいですか?お話伺っても」って。
ダメって言われたら当然帰りますよ。
いいって言うんで、まあ(家に)上がらせていただいた」
林修「まあ普通なかなかできないこと。度胸がある…」
市川團十郎「できないですよね。僕、そんな事ばっかりしてましたね、若い時はね。」
林修「他の家にもこう…」
市川團十郎
「あります あります。「ママ 海老蔵来たよ~」とか言って。
「えー何?なんですか?」。「ちょっとよろしいですか?」とかありましたよ。
だから別にその、知りたいことがあって。
でも、向こうは認識してくださってるじゃないですか。
ふふぁふあふあふあふあ(笑)」
昔の歌舞伎座での主役は権力争い
刺し違えるぞ!くらいの意気込み…本当にすごかった。だから、面白かった
林修「そもそも市川團十郎という名前の重みがもう全然違うじゃないですか」
市川團十郎「大変ですよね。どうしてなっちゃったんでしょうね…」
林修「でもあの、もう色々聞いていいですか?」
市川團十郎「ヒマなんで僕」
林修
「やっぱその歌舞伎座でこの主役をはるっていうのは、なかば取り合いというか…その権力争いみたいのがあるみたいなのが書かれてるんですけれども」
市川團十郎「昔はありましたね」
林修「で、1回(主役を)譲るともう二度と返ってこないとか」
市川團十郎「あ、そう。昔ありました」
歌舞伎座といえば、世界で唯一の歌舞伎専門の劇場。
そこで主役をはることは、役者たちにとって特別なこと。
市川團十郎
「やっぱり昔はそういうところの先輩たちは、骨肉の争いがございました。
見てました、そういうのを。
だから私が10歳ぐらいの時の、60代、50代すごかったです。
もうここは絶対譲らないっていうのばかりでした。
今はだいぶ緩和されて。交通整備ができてるかなと。
もうすごかったですよ。
もう本当に刺しはしないけど、刺し違えるぞ!みたいな意気込みです、先輩たちは。みんなそうです。
「あの人がこの楽屋いるんだったら、俺はなに廊下で化粧するわ」って言って廊下で化粧する人とかね。
もうすごかったですから。本当にすごかったですから。
もう面白い人は、なんか「弟の部屋がこの間口で、俺の部屋が弟の間口より3センチ狭い。なんだ!」って言って、メジャー持ってきて測るやつとかね。
測ってましたよ、おじいちゃんが。
もう本当に大変な時代ですよ。
だから面白かった。
もう入り乱れるから。ああ、面白かったですね」
林修「今はそういうパワーは逆に」
市川團十郎「みんなないですよね」
林修「まあ、まあ、日本人全体からそういうパワーが消えてる面もありますけれども」
市川團十郎「そうですね。みんな争わず。なにか穏便に穏便にみたいな。つまんないですね(笑)」
幼少期
1977年 13年続く名門 宗家「成田屋」に生まれた市川團十郎。
わずか5歳で初お目見えの舞台に上がり。
そして、7歳の時には、市川新之助の名を襲名。
師匠であり父でもある12代目市川團十郎のもと、大名跡を継ぐ道を選んだ。
幼少期は内気な子 小5ぐらいからエネルギーを出し始める
林修「え、小さい頃どういうお子さんだったんですか?」
市川團十郎
「小さい頃は、意外とこう内気な子でしたね。
でも、実際自分の中のエネルギー値を分かってたんで。
ぼちぼち出してこうかなって小5ぐらいからね。
むふふふふ(笑)」」
数えきれないほど怒られた…代々伝わる伝統の刀を折ってしまったエピソード
林修「でもそのお父様に若い頃には怒られたこともあるんじゃないですか?」
市川團十郎「いっぱいありますよ。いっぱいありますよ。そんな数えきれないですよ」
林修「ちょっと教えてくださいよ」
市川團十郎
「えっとですね。
初代團十郎っていうか代々の團十郎から伝わっている刀っていうのがありまして。
その刀をねこう大事に父は守ってですね。
でちょうど私、(父の)12代目團十郎 襲名披露興行の時ですね。
私が6歳か7歳。
で、口上というもので。
團十郎家は刀をさして、肌を脱いで、三宝を持って、こうやってにらむんですね。うわーっと、睨む。
これが吉例行事。襲名の時の。
そん時、刀がそれが代々伝わってる刀なんですけど。
それを「新之助これを持て~」っていうと「はは~」って言ってこれを(父に)持って行く役が私だったんです。
でその刀をこうやって持って、まあ楽屋から来て、舞台裏でこうさして待ってるんですけど。
その日はなんかお弟子さんと遊んじゃって…」
林修「はあ…それ神聖な日ですよね?」
市川團十郎
「そう。遊んじゃって。で、お弟子さんも悪いんですよね。向こうにいるから。
「ここだよ~」つって。
で、行こうとしたら行けないんですよ。なんだかしんないけど。体が進まないんですよ。
「待って」って言ったら、バキッっていったんですよね。
で、なんか「なんだろう?」って言ったら、あ、折れてんじゃんみたいな。
そしたらもうこれ舞台にすぐ持ってくやつだから。もう代々の刀。
みんな裏(方)の人が顔がもう蒼白となって。どうすんだ!って話になって。
「もう似たようなもの持ってくしかない」みたいなこと言い出して。
それで「上座の2階にある短刀がちょっと似てるじゃないか」つって、バーッてみんな走っていって。
「すみません、お借りします」つって、お借りして持ってくわけですよ。
「新之助」「はは~」って。まあ、ちょっとこっちも悪いなと思ったんですけれども。
で、持ってったら、刀さす前に違う刀じゃないですか。
持った瞬間に、皆さま(=お客さん)睨む前に睨まれましたね。(笑)
それでなさったんですよね、父は。
ほんでまあ、悪いかなと思ったんですけど、その後の怒りっぷりは久々にすごかったっすね。
でまあ、悪かったなと思いましたけども、「子供が歩いてつっかえたぐらいで折れるような刀を子供に持たせるなよ」って心の中で思ってましたよ。(笑)
だから僕はこれを作り変えると。
作り変えるからもう子供が持とうが何が持とうが折れないような刀に作り替えて、13年目からは中はほんびん?(=鉄製)にしましたよ。
13年目からはほんびんにしました。鉄にしました。
もう誰がやろうと折れないぞと。
ふふぁふぁふぁふぁ(笑)」
歌舞伎に対する意識が変わった瞬間(17歳)
17歳までいつか辞めようと思っていた
自らの意思で飛び込んだ歌舞伎の世界。しかしいざ中に入ってみると…
林修「この稽古自体はつらかったと?」
市川團十郎
「もう大変な稽古ばっかりでしたね。
この後の7歳以降の10歳になる連獅子の稽古なんかは父じゃなくて別のお弟子さんが教えてくれてたんで。毎日2時間。
僕だってあのー10歳で椎間板ヘルニアになりました。稽古しすぎて」
林修「いつか辞めてやろうと思われてたっていう話も」
市川團十郎「若い時は」
林修「あ、それどのくらいまで思われてた?」
市川團十郎「17(歳)前ぐらいですね。辞めようかなと思ってました。大変なんで」
カッコよかった祖父の歌舞伎映像…「自分の人生をかけてもいい」と思った瞬間
林修「でもじゃあ、逆になぜ続けようと思われたんですか?」
市川團十郎
「それはやっぱ、父と母の愛も大きいんですけど。
その実はその、12代目の父の11代目(祖父)は早く死んでるんですね。
ですから、会ったことないんですよ、私は祖父に。
で、ちょうど祖父が亡くなって30年っていう時が、私17歳だったんですよ。
そこで祖父の(歌舞伎の)映像を初めて見たんですよ。
で、歌舞伎ってそれまでの印象は、「長いな」とか「意味わかんないな」とか「つらいな」とかいうことあったんですけど。
祖父を初めて見たときに、映像ですけど。
「え⁉こんなカッコいいヤツ世の中にいるの?」っていう風に思ったんですよ。
私の中で、歌舞伎と祖父は別だったんですよ。分かります?
だから、私は祖父を見て、「ああ、これが歌舞伎であるならば、自分の人生かけてもいい」と思ったんです。
だから17歳の時に決めたんですね。やろうかなって。
「こんなカッコいいヤツいるんだな。しかも自分のじいちゃんか」みたいな」
舞台上での祖父の姿を観て、市川團十郎という歌舞伎界最高峰の名前を継ぐ覚悟が決まった。
伝統を守り、新しいものを取り入れる
由緒ある宗家である團十郎家
歌舞伎界には、宗家市川團十郎家にしか許されないものがある。
林修「歌舞伎役者さんがたくさんいらっしゃる中で、宗家っていうのはもう…」
宗家:江戸歌舞伎における中心的な存在の家系
市川團十郎
「歌舞伎役者のなかで宗家はたぶんウチだけだと思います。
だからあのそこ(=團十郎家)しか許されないものいっぱいありまして。
カツラとかもですね。あのウチは鬢付け(びんつけ)ついてて。まさかりっていう頭なんですけどね。
だいたい團十郎以外はくしめという後ろ髪なんですよ。
でも團十郎だけは油付きって言って、もうピッカピカに磨き上げるとか。
そういう歌舞伎の伝統文化って、見えない所での工夫とかもあって。
まあそういう意味ではやっぱ重荷が大きいですけど…。
どうしてなっちゃったんでしょうか?」(笑)
林修「もうでもそれは生まれた時から決まってたわけですもんね」
市川團十郎
「でも、やっぱり実績が伴わない場合はできないわけですから。
まあ、一応私なりに頑張って来たということなんだと思うんですけど。
あんまり理解されてないかなっていう」
歌舞伎十八番…実際のハコは誰も知らない場所に置いてある
父から受け継いだものの中には、(市川宗家の家の芸)歌舞伎十八番がある。
市川宗家の家の芸として選ばれた18種類の歌舞伎演目のことで、その台本は代々の当主がハコに入れて大切に保管していたことから、いつしかお家芸を「十八番(おはこ)」と呼ぶようになったという。
林修
「あの、本当に「十八番(おはこ)十八番(おはこ)」って世間は言いますけど。その物理的に箱がある?」
市川團十郎
「もちろん もちろん、ええ。7代目市川團十郎(1791~1859)が歌舞伎十八番っていうものを制定する時に、まあ色んなお話があるんですよね。
何のために作ったかとか、どういういきさつがあったのかとか全部割愛して、それを大切に箱の中に…こう桐箱の中にこうやってしまってますね。
でも(箱が)あることは、みんな知らないですね。
だから、出てないんで、外にね。
オハコの中に丁寧にしまってるから「十八番」」
林修「じゃあ、お家の中にはとんでもない…」
市川團十郎
「あ、お家の中には置いてないです。お家の中に置いといたら大変じゃないですか、そんなの。
別に、別においてます。
そうです。保管庫っていうか、人目につかない。誰も知らないです。
ウチの家族も知らないんじゃないですか」
林修「まあでも、将来的に新之助さんがそれを(継ぐ)?」
市川團十郎「まあ、そうですかね」
現状維持は右肩下がり。新しいことも取り入れることが伝統を守ることに繋がる
團十郎は江戸時代から続く歌舞伎18番で演じられなくなった演目を現代に復活させ、伝統を守る一方で。
宙乗りとプロジェクションマッピングをコラボさせたり、リアルタイムCGでライブ配信するなどして、若い世代や世界にも日本の伝統文化・歌舞伎を広めている。
古くから残る伝統を大事にしつつ、現代の要素を取り入れて新しい歌舞伎を作っている。
そこにはある想いが…
林修
「その変革にあたって、こうこの表現が妥当かどうかわかりませんけれども、その抵抗勢力と言われる存在は外部に多いんですか?内部に多いんですか?」
市川團十郎「内部ですね、はい。閉鎖的な世界なんで」
林修「まあでもそれ一方で言うと伝統を守るってことに非常にこう使命を…」
市川團十郎
「固執してる方々も多いわけじゃないですか。
で、それが全てじゃないじゃないですか。
あの、伝統守るから、伝統やってれば守ってることになるってわけでもないじゃないですか、うん。
だからやっぱり、伝統もやる。そして新しいこともちゃんとする。っていうことが、伝統を守るってことなんで。
やっぱ何かにこう凝り固まっている事って、うーん、現状維持かもしんないですけど、今の日本だと、現状維持は右肩下がりじゃないですか。ね?
だから、そういった認識を持ちながら、やっぱり右肩上がりでたぶん水平線なんですよね。
ですから、そういう認識でいたいですね」
江戸時代。歌舞伎は、当時の最新の事柄を取り入れて進化してきた。
だからこそ、今の時代の最新を迷いなく歌舞伎に取り入れ、次世代へ継承していく。
それが、宗家 市川團十郎の流儀。
(スタジオで…)
ハイヒールモモコ
「團十郎さんはね、ホントスゴイの。
なんか文句言う人おるやん?で、舞台観ろよと思うねん。
スゴイねん。明らかに違うねん。なんかね。空気感も変わる。
ほんでもう、圧倒的なこう舞台姿。
もう花道の後ろからカーテン シャッってやったとき「来はるで…」ってなるぐらい」
母・麻央さんの言葉が子供たちの支えに
1度きりの人生だから、なりたい自分になる
今年(2024年)10月、團十郎と息子・新之助は親子での連獅子を披露。
2人の子供たちにとって、どんな師匠なのか?
ぼたん
「普段普通に稽古を先生がしている中でしている時も、お父さんが見ているときは指導してくれたりとかしますね。
細かい所もそうですし、全体的なところも教えてくれます」
新之助「厳しい時もありますけど、普段は優しいですよね」
ぼたん
「稽古しているときに父が見ていると、なんか安心している気持ちもありながらいつもより緊張するっていう。
お父さんの背中を見ていて、あの本当に考えさせられたりとか、学ばせてもらったりとか。
やっぱり、カッコいいなって。
そういうところも尊敬しますね」
父・團十郎と同じ舞台に立つことも多い新之助くんだが、初めて舞台に上がったのは2歳8か月の時。
当時その初お目見えを誰よりも楽しみにしていたのが、新之助君の母・小林麻央さん。
そんな麻央さんに背中を押されたのは、新之助君だけではなく、ぼたんさんも。
それは数年前、自分の進むべき道が見つからず悩んでいた時のこと。
スタッフ「なんかお父さん(=團十郎さん)が1度きりの人生だからっていう言葉を言ったっていう…」
新之助「それはママの言葉ですね」
ぼたん「将来何になりたいって今聞かれても、これになりたい!っていうのが本当になくて」
その時に思い出したのが、母・麻央さんが治療中に書いたこの文章。
『なりたい自分になる。人生をより色どり豊かなものにするために。だって、人生は一度きりだから』
その結果…
ぼたん
「あの、事務所にも新しく所属させていただいて。
なんか、新しい一歩を踏みだせたみたいな。
その言葉に押されたっていうところはあったと思います」
そして最近母・麻央さんについて父・團十郎からこんなことを言われたという。
ぼたん
「最近なんですけど、父自身から言われたのは、あのお父さんの性格にもあるし、お母さんみたいな性格も入ってるから、絶対ママの方に似てねって」
新之助「(姉・ぼたんさんには)お父さんのやんちゃな性格とお母さんの優しい性格が入ってると思います」
何かの時に子供たちの支えとなる麻央さんの句
林修「ご覧になっていかがですか?」
市川團十郎
「いやーなんか、麻央が初お目見えをこう勸玄(かんげん)の舞台を観てる客席の姿あるじゃないですか。
まあ、それが1つの僕の人生の夢だったんですよね。
なんかこう、麻央が自分の子供の初舞台なり、初お目見えを客席でああやって観る。
やっぱり自分の息子が…まあ、娘が歌舞伎の舞台に立って、それを初めて見る時って、たぶん母親ってすっごい幸せなんだろうなって自分の母を見てても思うし、他のお家の方々見てても思ってたんですよ。
だから、絶対これを体験してもらいたいっていうのがもう心の底から私は思ってまして。
まあそれ今、ちょうど映像として残ってたんで。
見て、「ああーよかった。ここだけはちゃんと観れててくれてんだな」と思いながら、はい」
林修「ぼたんさんは麻央さんの言葉が背中を押してくれたと」
市川團十郎
「その話はね、うん、僕も思います。
やはり彼女が残した句がやっぱり子供たちの何かの時に、重要な決断をするときに必要な言葉だなと思います」
團十郎さんの母からの教え
どんな嫌なことがあっても、寝たら忘れる
一方、團十郎自身も母からの教えが今の市川團十郎としての礎になっているという。
林修
「あの、ご自身のお母さんからは何かこう、こういうこと学んだっていうことはおありですか?」
市川團十郎
「ウチの母から学んだことは。
母はね、どんな嫌なことがあっても、何があっても、寝たら忘れるんですよ。
え、これ忘れてんの?って子供の時僕、私が頭おかしいのかな?って思うぐらいな。
あの、色んなことが起こるじゃないですか。
で、めちゃくちゃ怒られることもあるわけですよね、母親だから。
それで次の日気まずいなぁと思うと、全然覚えてない。
で、覚えてないふりをしてるのかな?と思ったら、覚えてないんです。
だから「なんだ?」と思って、いろいろ確認するわけですよ。ホントに覚えてないのかな?
そしたら、ほんとに覚えてないんですよ。
だから、これ見習おうと。嫌なことがあっても忘れる機能を搭載しようと。
恐らく自分も母親の子供なんで、悪いことがあっても忘れる機能を必ず搭載してると思って、はい。
ということで、発動するようにしました」
林修「で、実際発動されてますか?」
市川團十郎
「まったく気にしないです。次の日何にも気にしないです。
はい。新しい1日としてフレッシュに起きてます」
林修「まあでも、それは一つの生き方ですよね」
市川團十郎
「そうそう。引きずっちゃったら、寝れもしないじゃないですか、きっと。
あの、横になったら、僕2秒で寝れます」
挫折はない
林修「でもご自身としては、何か挫折っていうことはおありだったんですか?」
市川團十郎「ないです」
林修「ああ、いいですね。挫折ないって」
市川團十郎「はい。挫折って何ですか?」
林修「まあ、くじけて立ち直れなくなるような辛いこと」
市川團十郎
「ああー。ないですね。
いや、短期的な問題であって、長期的な問題ではないと。うん。
だから、短期的な問題をいかに自分の中で栄養素として生きられるかっていうだけの話だと思うんで。
だから、そういうことが大事なんじゃないですか。うん。
だから今、現在があるんでしょうね」
日々変化する感情に翻弄され、やるべきことをおろそかにするのではなく、嫌なことは忘れて、自分のやるべきことにまい進する。
團十郎は母からの学びを実践し続けている。
團十郎さんの父からの教え
そして、父であり偉大な師匠でもある12代目市川團十郎からも人生の重要な指針となる教えを受けていた。
團十郎の父、12代目市川團十郎と言えば、古典歌舞伎の歌舞伎18番を復活させるなど、現代歌舞伎に貢献。
休むことなく歌舞伎を演じ、それは時に、病を患っても舞台に立ち続けた偉大な人物。
学者のような人だった…丁寧に色んなことを教えてくれた
林修「あの偉大なる先代、お父様の教えで何か今でも覚えていらっしゃることありますか?」
市川團十郎
「いっぱいありますよ。
やっぱり父も丁寧に色んなことを教えてくれましたからね。
あのー世の中のこととかね。もちろん歌舞伎のこと。あと、人間の欲というもののこととか。
やっぱり父の場合は、どちらかというと、学者のような人だったんで。
歌舞伎俳優という肩書ですけど、学者だったので」
(スタジオで…)
ハイヒールモモコ
「市川家は「にらみ」っていうのがすごいのよね。
ほんまにあの「にらみ」を受けたら、あの病気せえへんって言うねん。
無病息災って言われてんねん、團十郎さんのは」
自然の華がある役者は出てくるだけでいい
林修
「この本読んでても「華のある役者」と「華のない役者」っていうことがはっきり出てまして。書かれてまして。
でも、この役者として華があるないってことについてはどう思われてますか?」
市川團十郎
「これはね。自然の華と造花と2パターンあると思うんですけどね。
でも基本的には、自然の華がもう9割9分だと思うんですけどね、うん。
で、自然の華を持ってらっしゃる方っていうのは、私も何人か拝見しました。
特に先輩に多かったですね、はい。
で、その方が出てきたらば、もうそれでいいんですよ。出てきただけでいいんですよ。
何にもなさんなくたっていいんですよ」
林修「それをお客さん観に来ると」
市川團十郎
「そう。そして、そういう域に達した年齢の達した歌舞伎俳優は、それを認知してるんで。
その上での芸事になってますよね。だから、それは見事ですよ。
だから歌舞伎って面白いのは、若いうちはできないんすよ。上手いことできないんすよ。
やっぱり、キレイだな、華があるな、華やかだな、かっこいいなはあるんですけど。
芸事は充実しないですよね。
やっぱ年齢と共に充実して。
自分が出来るって頃には、自分の見た目は老いてるっていう。
まあ、複雑な関係なんですけど。
まあ、そういう芸事の継承っていうのが面白いと思うんですね」
林修「今おっしゃった造花っていうのは?」
市川團十郎
「あ、造花っていうのはね、できるんだと思うんですよね。一時的に。その場しのぎで作れますね。うん」
林修「じゃあやっぱりその、努力でこう何とかなる部分よりもやっぱり持って生まれた…」
市川團十郎「(華は)持って生まれたものでしょうね」
(スタジオで…)
ハイヒールモモコ
「ほんまに、舞台に立ちはったら、華が見えるぐらいの華がある方は、團十郎さんやなって思うんですよね」
変わりづらい歌舞伎の世界
男性が舞台に上がる歌舞伎の世界…しかし、元々歌舞伎は女性から始まった
そう。市川團十郎の歌舞伎は、最も華があると言われ、来年(2025年)1月にも舞台に立つ。團十郎は忠臣蔵で4役を演じ分ける。
また、今回の舞台では娘の市川ぼたんとも共演。
しかし歌舞伎の世界では、寺島しのぶや松たか子も歌舞伎の舞台に立ってはいるものの、今でも男性だけが立つものという古くから慣習が強い。
林修
「でも歌舞伎の世界でこのお嬢様ですよね?息子さんだと我々方向が見えやすいと思うんですけど、お嬢様に対しては、今どんな思いでみてらっしゃるんですか?」
市川團十郎
「いや、全然いいんじゃないですかね。歌舞伎のこと挑戦し続けて。
やっぱりそれはもちろん色んなこと言う方いらっしゃると思うんですけど。
私の中では、元々歌舞伎は出雲阿国というね。
もちろん林先生はご承知でしょうけど、女性から始まって。
まあ、風紀的な問題で女性が舞台の上に上がれないということの中から、まあ女を演じる男、女形というものが生まれたわけですから。
まあそういう意味でこう色々と紆余曲折しながら、現在に至ると。
ちょうどウチの妹もいましてね。(市川)翠扇(すいせん)っていうね。
彼女もやりたいって気持ちあったでしょうけど、まあ時代の波でね、なかなか難しかった。
(松)たか子ちゃんもそうだったと思うんですよ、うん。
ですがまあ、なかなか難しい。
ということですが、今はね。そんなことも言わなくてもいいっていう世の中に徐々になってきてるんで。
まあ、1月の舞台も彼女出ることになりましたし」
休演日がなかった…病気でも舞台に立ち続け
林修「(歌舞伎界は)変わりづらいって思われますか?」
市川團十郎
「思いますね。いろんなものが変わりづらいです。
例えば、歌舞伎の休演日とかも今ではあるんですけど、僕がしようっていう風に動き出して。
なかなか動かなかったですね。
今や休演日が当たり前になってきたんですけど。
だからもういろんなものが変わりづらいですね」
林修「25日ぶっ通しで?」
市川團十郎
「そう。ぶっ通しで。大変です、だから。
朝から晩まで25日間ずーっと舞台出るんで。
だからもう本当に心身ともにボロボロになる方が多い。
だから、体調崩しても歯医者も行けない。病院もいけない。
しかも今みたいに風邪ひいても休めない。
特に晩年の大先輩たちは、もう肺にがんが患ってらっしゃっても出てたりとか」
父の言葉「私は休むことを学べば良かった」
團十郎が休演日を設けるべきだと強く思ったきっかけ。
それは、歌舞伎に人生をかけてきた父からの言葉だった。
亡くなる2か月前、父は病室のベッドの上でこう言ったという。
市川團十郎
「父はあの12カ月中11か月歌舞伎の舞台立ってたんですよ。
まあ、歌舞伎が好きでしたし、歌舞伎のためにと思ってなさってましたが。
だから父は、2013年の2月の3日に旅立つんですけど。
2012年の12月 私が病室に行った時に、ふと2人になった時に喋った言葉が、やっぱりこう…残りますね。
まあ、一言しか言わないんですけどね。
あの、「私は休むことを学べば良かった」と、うん。って言ってました。
その言葉から、先ほどの私は休演日とか様々なことを想像しだしたと。
やはり、この歌舞伎のために生きるっていう人生。
でも、歌舞伎のために生きるんですけど。
自分の人生というものをどういうものであるかってことを認識しないといけないってことをその一言で私も感じました。
ですから、歌舞伎を重要に思って歌舞伎のために生きますというのは、自分の人生っていうものを麻央の言葉もあったけど、なりたい自分になるということをやっぱりこうもっと掘り下げないと、芸事も面白くなんないだろうなと思うんで。
そういうことを父の一言から感じました」
歌舞伎俳優市川團十郎として、そして2人の父親としても、なりたい自分になる。
それが、尊敬する父と最愛の妻から学んだ人生訓
仕事をする上で大切にしていること…「楽しむこと」
林修「團十郎さんが仕事をする上で大切にしていることを教えていただけますか?」
市川團十郎
「最近変わったんですよね。
あの、本当に簡単な言葉ですけど、「楽しむこと」。
昔までは楽しめなかったんで」
林修「以は何を大切になさってたんですか?」
市川團十郎
「義務、責任、責務、やり切る力。
そういったものに対して、やっぱり自分を追い詰めて追い詰めて向き合ってましたね。
が、團十郎襲名をして変わったことは、楽しめるようになってきたと。
うん。ようやく。
ですから、今は楽しむことを大事にしてます」
人生を楽しみ、嫌なことは忘れる。
この豪快さこそが市川團十郎の真髄なのだ。